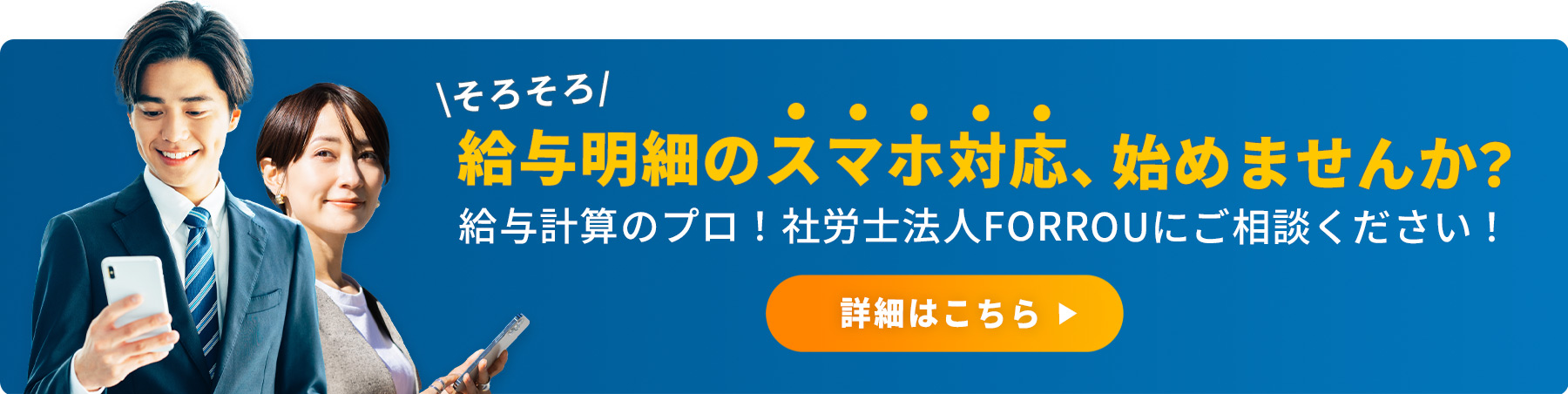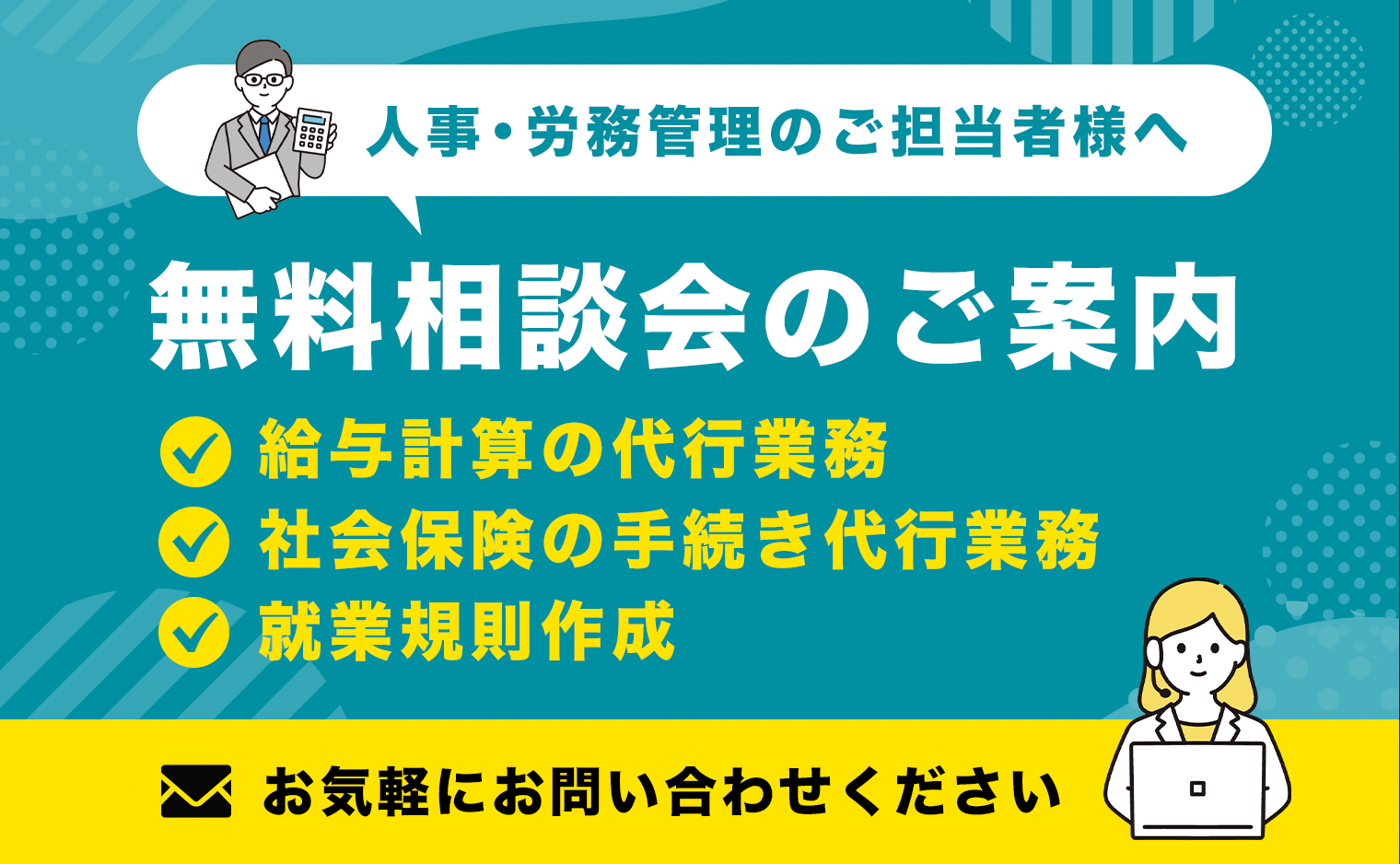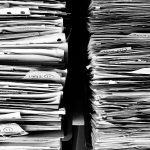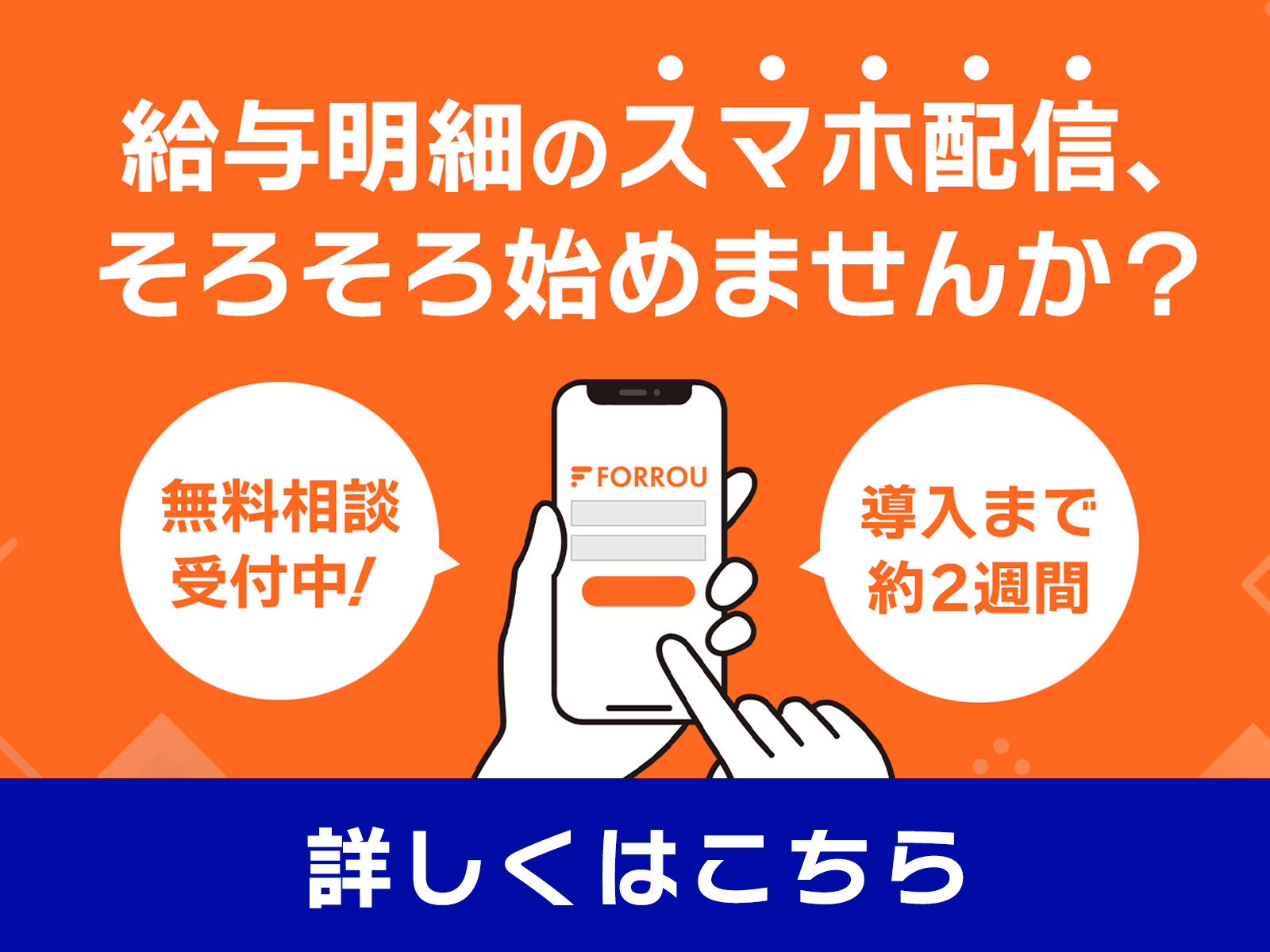新型コロナウィルスの感染拡大により、多くの企業が従来通りの営業ができない状況にあります。とくに、外食・小売・宿泊・娯楽産業などでは、長い「休業」を余儀なくされた企業もたくさんありました。会社都合の意思決定により、従業員を休ませた場合、企業は従業員に休業手当を支払わねばなりません。その休業手当の一部を肩代わりする制度が、「雇用調整助成金」です。
「雇用調整助成金」は、すでにある制度を新型コロナバージョンに一部見直し、運用されています。ところが、この見直しの頻度が高く、「結局、現段階ではどうなっているの?」という声をよく聞きます。そこで本記事では、2020年6月15日時点での「雇用調整助成金」の制度概要、申請の仕方についてご紹介します。
2020年5月以降の大きな変更点
2020年4月20日に、同様の雇用調整助成金に関する記事(こちら)を掲載しました。掲載後の大きな変更点については、以下の9点です。
全企業対象
(1)初回を含む「計画届」の提出が不要に
(2)企業規模を問わず、上限額を8330円から1人1日15000円へ
(3)雇用調整助成金のコロナ特例期間を3カ月延長し、4/1~9/30へ
(4)「平均賃金」「所定労働日数」の算定方法を簡略化
(5)支給対象期間の初日が「2020年1月24日から5月31日」までの休業の申請については、
申請期限を2020年8月31日まで延長(※本来は事後2カ月以内)
(6)オンラインでの提出が可能に(※2020年6月15日現在、オンライン受付を停止中)
(7)出向特例措置を、緊急対応期間内においては「1か月以上1年以内」に緩和
中小企業対象
(8)解雇等を行わない中小企業の助成率を、一律10/10(100%)へ
中小企業のうち、「従業員20人以下」の小規模事業主のみ対象
(9)従業員20人以下の場合、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定可
いくつか細かな改正もありますが、5月以降の大きな変更点は「助成額の引き上げ」と「手続き方法の簡略化」の2点でしょう。
そのほか、雇用調整助成金制度の対象企業や、対象労働者については「前回の記事」と変更ありません。以下では、大きな改正のあった「助成額」と「手続き方法」を中心にご紹介します。
結局、いくらの助成金がもらえるの?
たび重なる見直しで、助成額(もらえる額)は徐々に増えています。結局のところ、現段階でいくらもらえるのでしょうか。
まず、大前提として、「上限額」については、すべての企業で一律15000円となりました。これまでの8330円からおよそ「倍増」したことになります。
そのうえで、最終的に、会社規模に応じて次のような助成率・助成額で着地しています。
大企業の場合
大企業の場合は、4月時点と変更はありません。
✓ 解雇などを一切行わない場合は、休業手当の概算額 ×3/4(75%)
✓ 休業中の労働者に対して教育訓練を実施した場合は、1人1日あたり1800円加算
※休業手当の概算額=「前年度の賃金総額」÷(「1カ月平均被保険者数」×「年間所定労働日数」)×休業手当支払い率(60%など)。詳細後述。
中小企業の場合
中小企業の場合は、再三の見直しをへて、現時点での最新版は以下のようになりました。
✓ 解雇などを一切行わない場合は、休業手当の概算額 ×10/10(100%)
✓ 休業中の労働者に対して教育訓練を実施した場合は、1人1日あたり2400円加算
| 大企業 | 中小企業 | |
| 解雇等あり | 2/3 (約67%) |
4/5 (約80%) |
| 解雇等なし | 3/4 (約75%) |
10/10 (約100%) |
中小企業(解雇等なし)の場合の助成率については、5月中に何度か見直しがありました。最終的に「一律100%」で落ち着きましたが、最新版の発表(こちら)は、6/12(金)に行われたばかりです。「すでに申請したものはどうなるのか?」と疑問をもちますが、これについては4/1分まで遡って適用となるそうです。すでに申請済みのもので、増加するものについては、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算してくれます。ですから、再度の申請手続きは必要ありません。
ただし、事業主が過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要です。
「雇用調整助成金」の申請方法は、どう簡略化された?
4月時点では休業の「計画届」が必要でしたが不要になり、手続きがシンプルになりました。具体的には以下の流れで進めます。
▼ 雇用調整(休業など)について労使協定を締結
▼ 雇用調整(休業など)を実施
▼ 休業実績にもとづき、「申請書類一式」を作成し、労働局かハローワークに提出
▼ 労働局にて審査
▼ 審査に通れば申請額が企業に振り込まれる
※判定基礎期間(賃金締切期間/大半は1カ月)ごとに提出
申請書類の書き方について、小規模事業主(従業員数20名以下)のみ大幅に緩和されました。ですから、小規模事業主以外(20名超)と、小規模事業主(20名以下)に分けて紹介します。