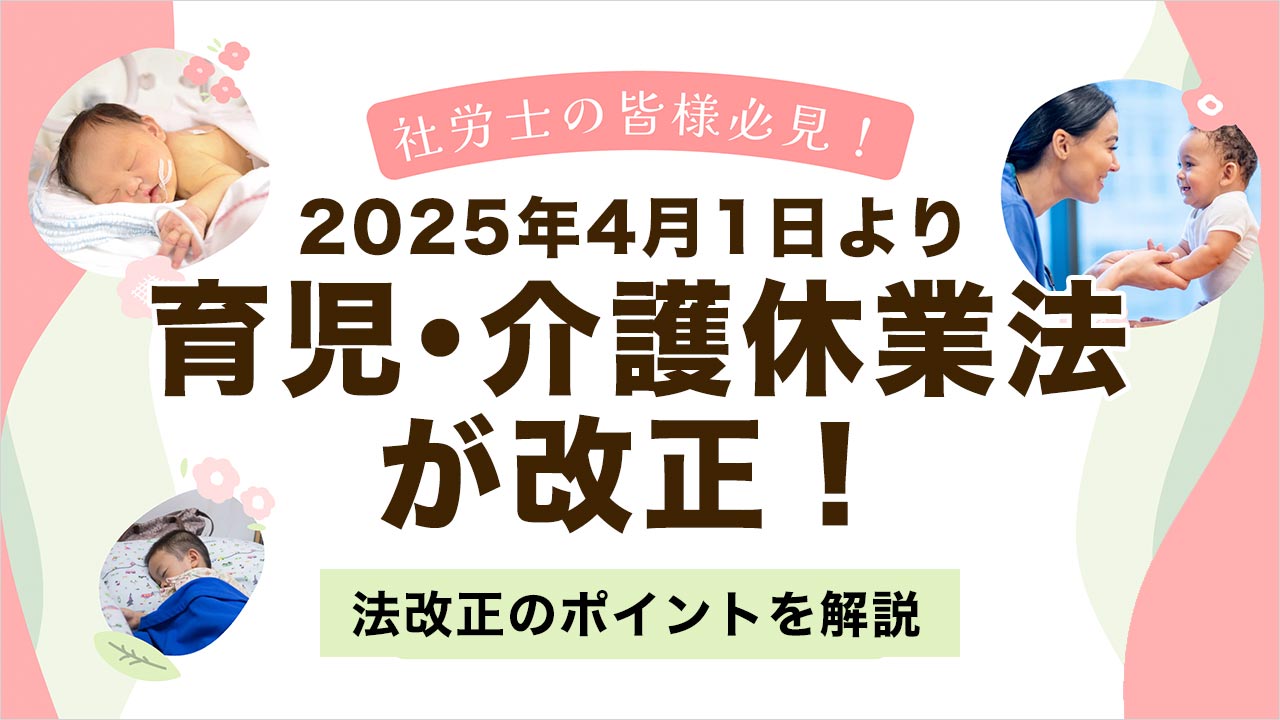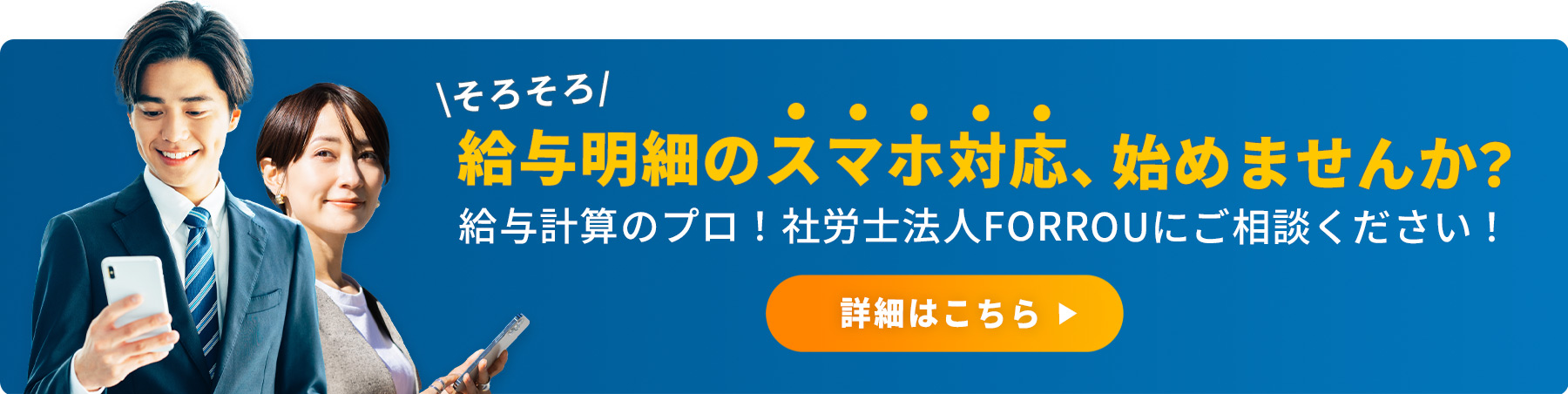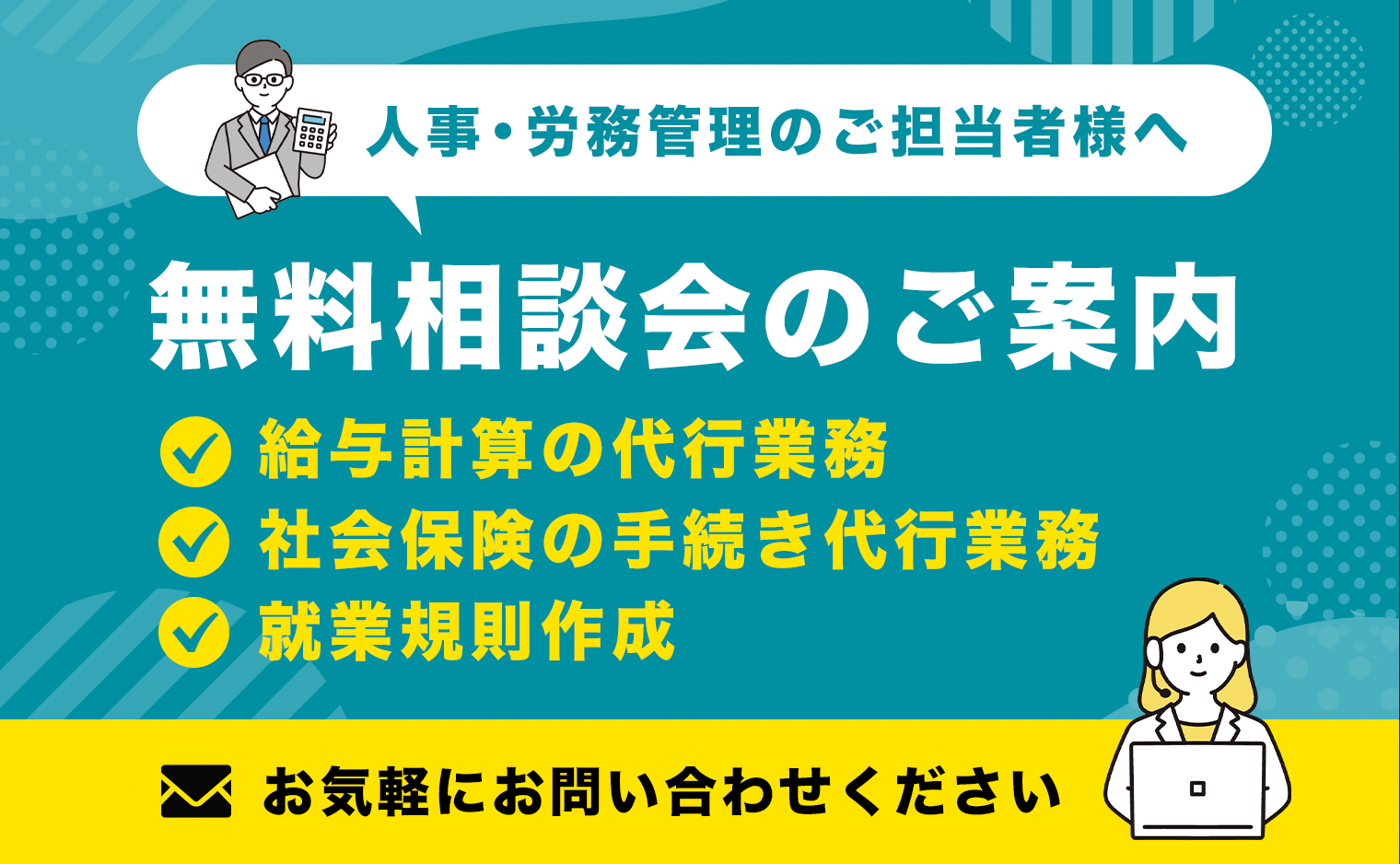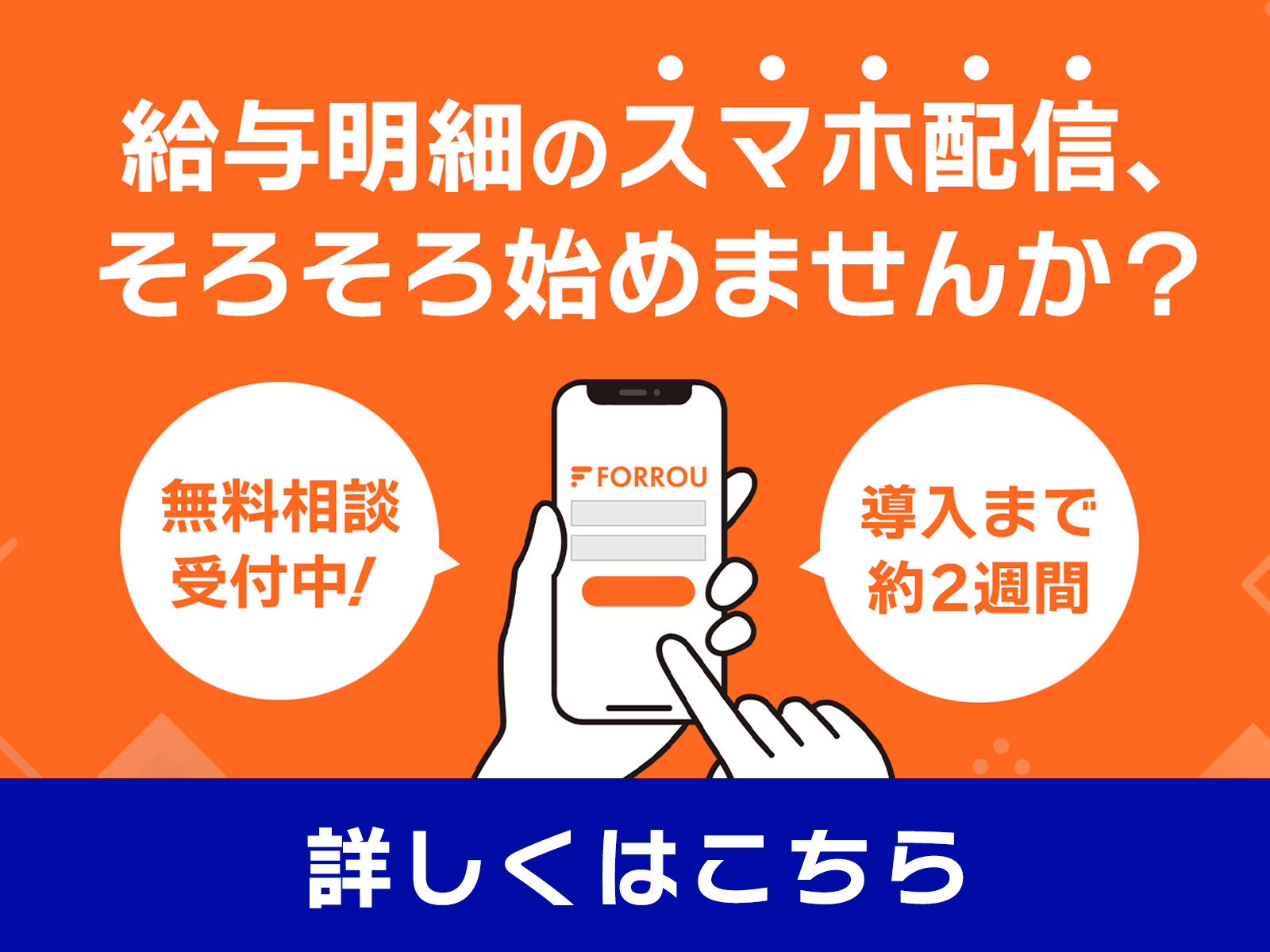2025年4月1日から施行される改正内容について、企業が対応すべき点を 義務、努力義務、就業規則の改定の必要性、労使協定の必要性に分けて改めて整理しました。
子の看護休暇の見直し
改正内容
- 対象年齢の拡大:これまで「小学校就学前」だった対象年齢を「小学校3年生修了まで」に引き上げ。
- 取得可能事由の追加:感染症による学級閉鎖、入学・卒業式の参加なども対象に。
- 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」
| 義務 |
企業は新たな子の看護等休暇制度を整備する必要がある。 |
| 就業規則の改定 |
必要(対象年齢の引き上げ、取得事由の拡大を反映) |
| 労使協定の必要性 |
既存の労使協定がある場合は見直しが必要(適用範囲が変わるため) |
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
改正内容
- 対象者の拡大:これまで「3歳未満の子を養育する労働者」だったが、「小学校就学前の子を養育する労働者」に変更。
- 該当者が請求した場合、事業主は所定外労働を免除しなければならない(事業の正常な運営を妨げる場合を除く)。
| 義務 |
事業主は対象労働者からの請求があれば所定外労働を免除する義務がある。 |
| 就業規則の改定 |
必要(対象者の範囲拡大を明記) |
| 労使協定の必要性 |
特になし(労働者個別の請求に基づく措置のため) |
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
改正内容
- これまで短時間勤務制度が困難な場合の代替措置として「フレックスタイム制」「始業・終業時間の変更」などが認められていたが、新たに「テレワーク」を追加。
| 義務 |
短時間勤務制度を提供できない場合、代替措置としてテレワークの導入が可能に。 |
| 就業規則の改定 |
テレワークを代替措置として導入する場合、改定が必要 |
| 労使協定の必要性 |
短時間勤務制度の代替措置を導入する場合、労使協定の締結が必要 |
育児のためのテレワーク導入
改正内容
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、企業に努力義務を課す。
| 義務 |
企業は可能な限りテレワークの導入を検討することが求められる。 |
| 就業規則の改定 |
導入する場合は必要(制度の具体的な運用ルールを明記) |
| 労使協定の必要性 |
特になし(努力義務のため、強制はされない) |
育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
改正内容
- 従業員数1,000人超の企業 → 従業員数300人超の企業 に拡大。
- 公表内容:
a. 男性の育児休業取得率
b. 育児休業等+育児目的休暇の取得率
| 義務 |
該当企業は育児休業等の取得状況を年1回公表する必要がある。 |
| 就業規則の改定 |
特になし(公表方法の検討が必要) |
| 労使協定の必要性 |
特になし |
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正内容
- これまで「雇用期間6か月未満の労働者」は介護休暇の対象外だったが、この除外規定を廃止。
- 週の所定労働日数が2日以下の労働者を除き、すべての労働者が介護休暇を取得可能に。
| 義務 |
企業は介護休暇の対象者を拡大する必要がある。 |
| 就業規則の改定 |
必要(対象者の範囲変更を反映) |
| 労使協定の必要性 |
既存の労使協定がある場合は見直しが必要 |
介護離職防止のための雇用環境整備
改正内容
- 事業主は以下のいずれかの措置を講じる必要がある:
a. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
b. 介護に関する相談窓口の設置
c. 介護休業・介護両立支援制度等に関する情報提供
| 義務 |
企業は上記のいずれかの措置を実施しなければならない。 |
| 就業規則の改定 |
特になし(内部規程での整備が望ましい) |
| 労使協定の必要性 |
特になし |
介護に直面した労働者への個別の周知・意向確認
改正内容
- 介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、事業主は以下の対応を義務化:
a. 介護休業や両立支援制度の情報提供
b. 意向確認(どのような支援が必要かをヒアリング)
| 義務 |
企業は労働者の申し出に応じ、情報提供・意向確認を実施する必要がある。 |
| 就業規則の改定 |
特になし |
| 労使協定の必要性 |
特になし |
まとめ
従来、労使協定を定めている場合は変更する必要があります。
また、就業規則の改定も必要です。
今年10月の改定では、以下の制度について施行となります。
- 柔軟な働き方を実現するための措置
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取
4月の改定では育児介護休業法について共通の法改正に対応、10月は会社独自の対応について考えるという段階的な移行です。
まずは、就業規則の改定、労使協定の再締結についてご検討ください。