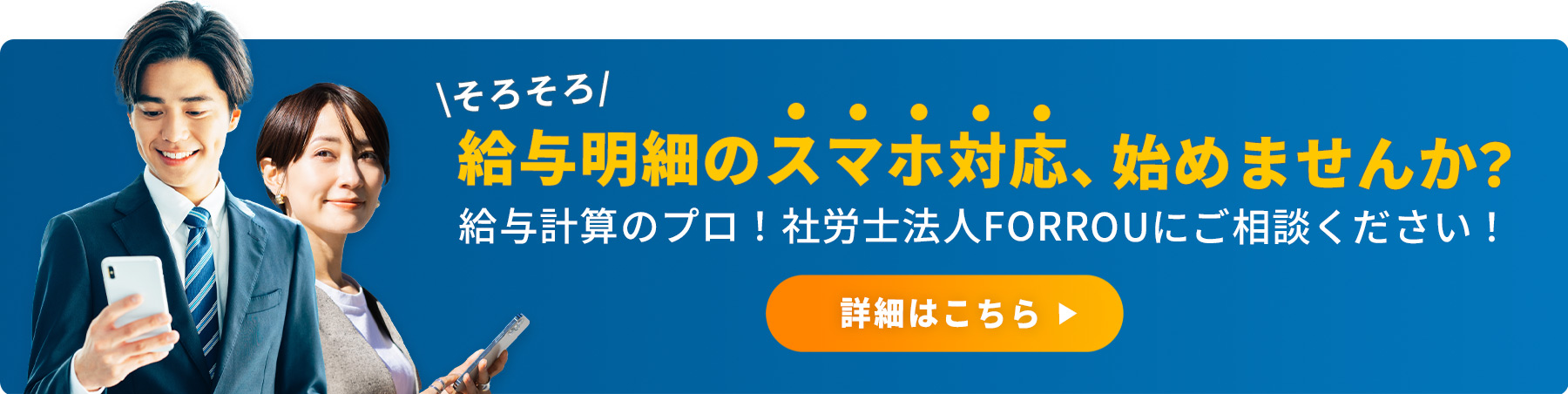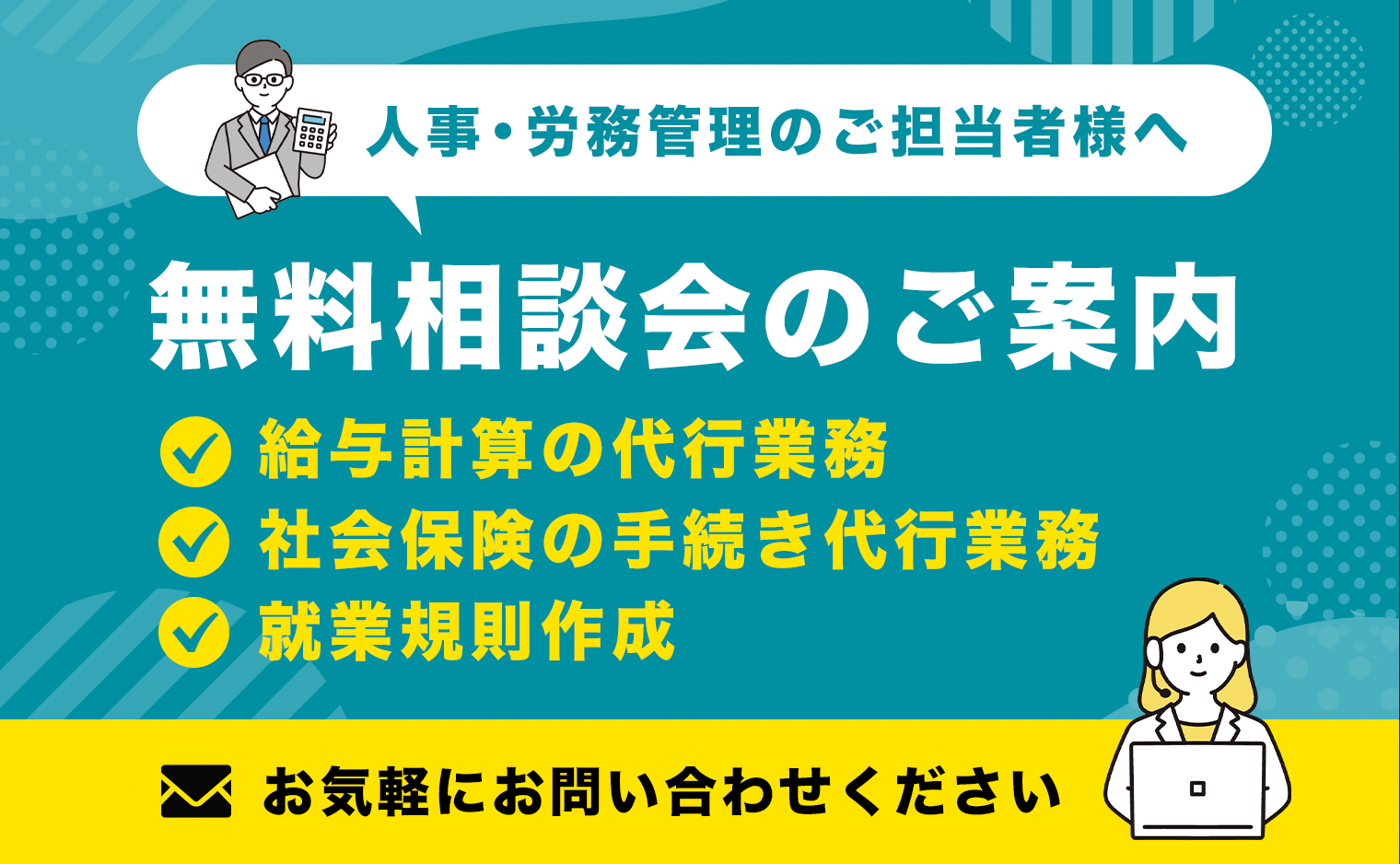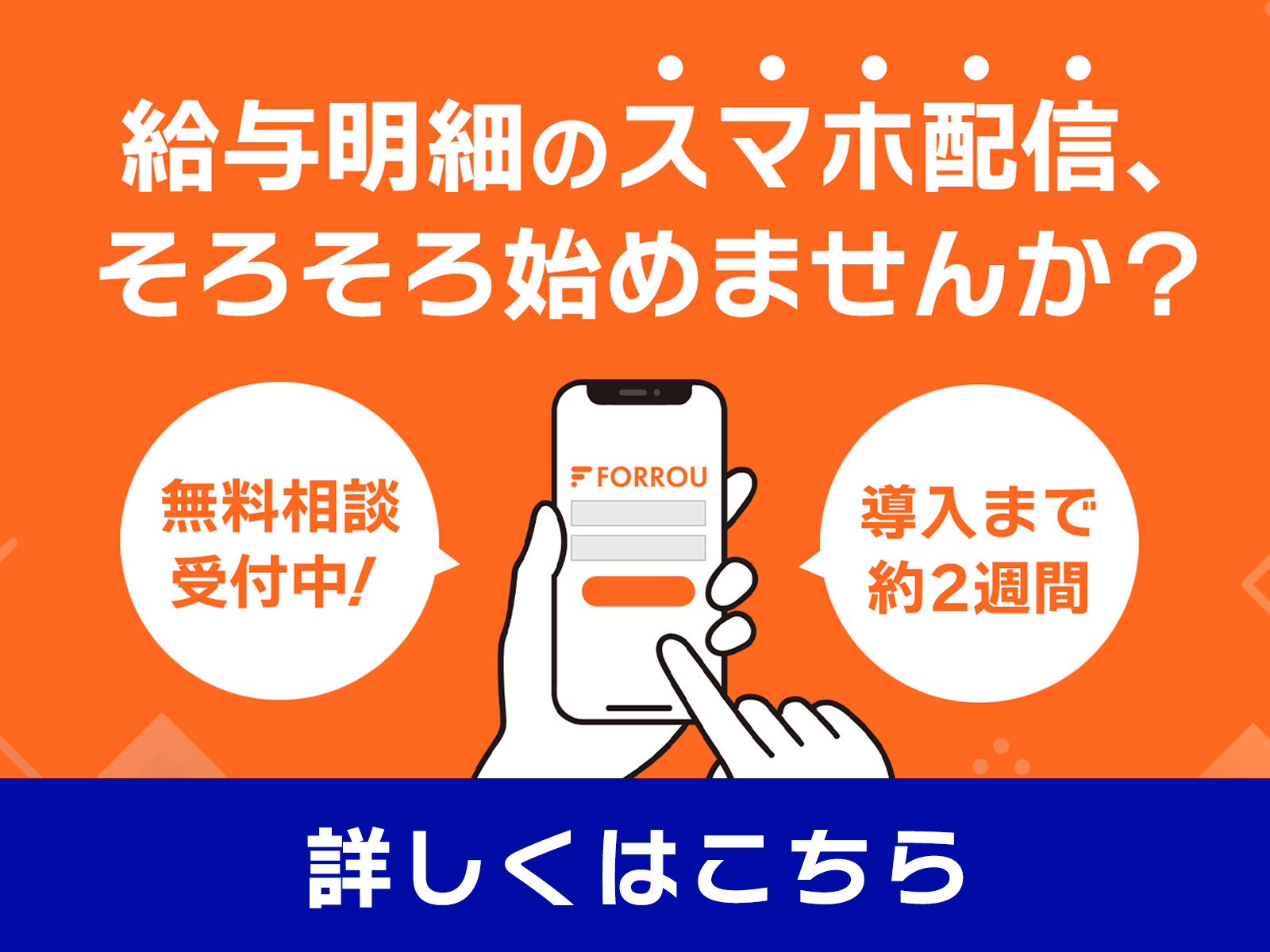中小企業の人事の悩みは尽きません。たとえば、
● 従業員が定着しないから採用経費がかさんでしまっている。
● 評価制度がないから勤続年数だけで給料を決定してしまっている。
● 先日もエース級の正社員に退職されてしまった。
● 当社は業界でも水準の高い給料を払っているのに、いったいどうして優秀な社員から辞めていくのだろう。
しかし、自社にマッチした人事評価制度を導入することで、こうした悩みを解決することができる可能性があります。
今回は、中小企業が取り組むべき人事評価制度構築のメリットについてご紹介させていただきます。
なぜ必要?人事評価制度
人事評価制度が必要となる理由については優秀な社員の定着率がアップするメリットと、社員間の給与や評価に対する公平感を醸造することが可能なためです。
優秀な社員ほど「一生懸命仕事をして高い成果を出しているのに、給料が変わらない」と不満を持つ傾向にあります。また、仕事が出来ない社員は社員で「会社が活躍の場を用意していないし、評価制度も不透明だ」と不満を持っています。
客観的にも分かりやすい人事制度を導入することで、仕事のできる社員も出来ない社員も納得感をもって仕事を遂行することができるようになります。
いま注目の人事評価制度コンピテンシー評価制度とは?
コンピテンシー評価制度とは、優秀な人材の出した成果と行動に基づいた人事評価の手法です。
具体的には会社の職種ごとに優秀な社員の業績を分析してモデルとして評価制度を策定する方式のことで、中小企業における優秀なエース級社員の定着に貢献すると期待されていますね。
従来の人事評価制度は上司の部下への好感度で評価が変動してしまうなどの問題がありましたが、コンピテンシー評価を導入することで個人に対する評価を客観的に付けることが可能です。
中小企業におけるコンピテンシー評価の具体的な手段とは?
成績優秀とされる社員だけではなく、優秀でないと判断されている社員の考え方や成果をヒアリングなどを実施して集めることが重要となります。
理由としてはコンピテンシー評価制度は「優秀な社員の行動や成果」をベースに決定される評価制度ではありますが、優秀とされる社員だけの意見を聞いてから評価制度を実施すると評価制度に偏りがでる恐れがあるためです。
人事評価制度の最終的な目的は「社員全員が目標に向かって努力できる」状態を構築することが目的のため、社員全員の意見をヒアリングする必要性があります。
優秀なモデル社員が社内にいない場合は企業理念などを評価対象とする
優秀なモデル社員が社内に存在しない場合には、企業理念のように「会社として絶対に社員に守ってほしい行動規範」を評価軸に設定する方法があります。
大企業の場合は評価基盤がしっかりしているケースも多いですが、中小企業では属人的な仕事が多くなっており、明確に「優秀社員」が存在しないケースもありますね。
その場合は企業理念などのように「全社員が意識すべきことを意識していることが前提」というものを評価軸に入れておくと納得感のある人事評価制度を構築することが可能です。
実際にコンピテンシーを導入した企業の事例
コンピテンシーを実際に導入した企業としては、「富士通」が有名です。
富士通ではコンピテンシー評価によって役職ごとに求められる仕事の成果を明確にすることで、曖昧になりがちな評価制度を一新しました。
職位などにコンピテンシー評価で優秀な人材の基準を設定して、評価を透明にすることで年功序列から実力主義の会社へと変貌した成功事例の一つです。
離職率が下がるなどの効果も出ており、コンピテンシー評価制度の威力の高さを物語っていますね。
大企業の導入事例ばかりが大きく取り上げられていますが、実際には中小企業の現場にも制度を導入することで、離職率の改善が行われる可能性があります。
大企業であっても中小企業であっても人の持っている感情は変わらないので、明確で公平な人事制度で処遇されていると感じることが出来れば、人は定着します。
【参考】井村直恵著作 日本におけるコンピテンシー ―モデリングと運用―
【参考】安田均著作 富士通新人事制度における成果主義と能力主義
【参考】富士通HP
曖昧な評価基準で離職する社員を減らそう
曖昧な評価基準で社員を評価するのではなく、コンピテンシー評価制度によって「優秀な社員」や「するべき仕事」の定義を明確化するようにしてみましょう。
大企業がやっているものをそのまま導入するのではなく、コンピテンシー評価制度はそれぞれの会社の社員のレベルに合わせて行える評価制度です。
実際に運用すれば、大きな成果が出る可能性があります。